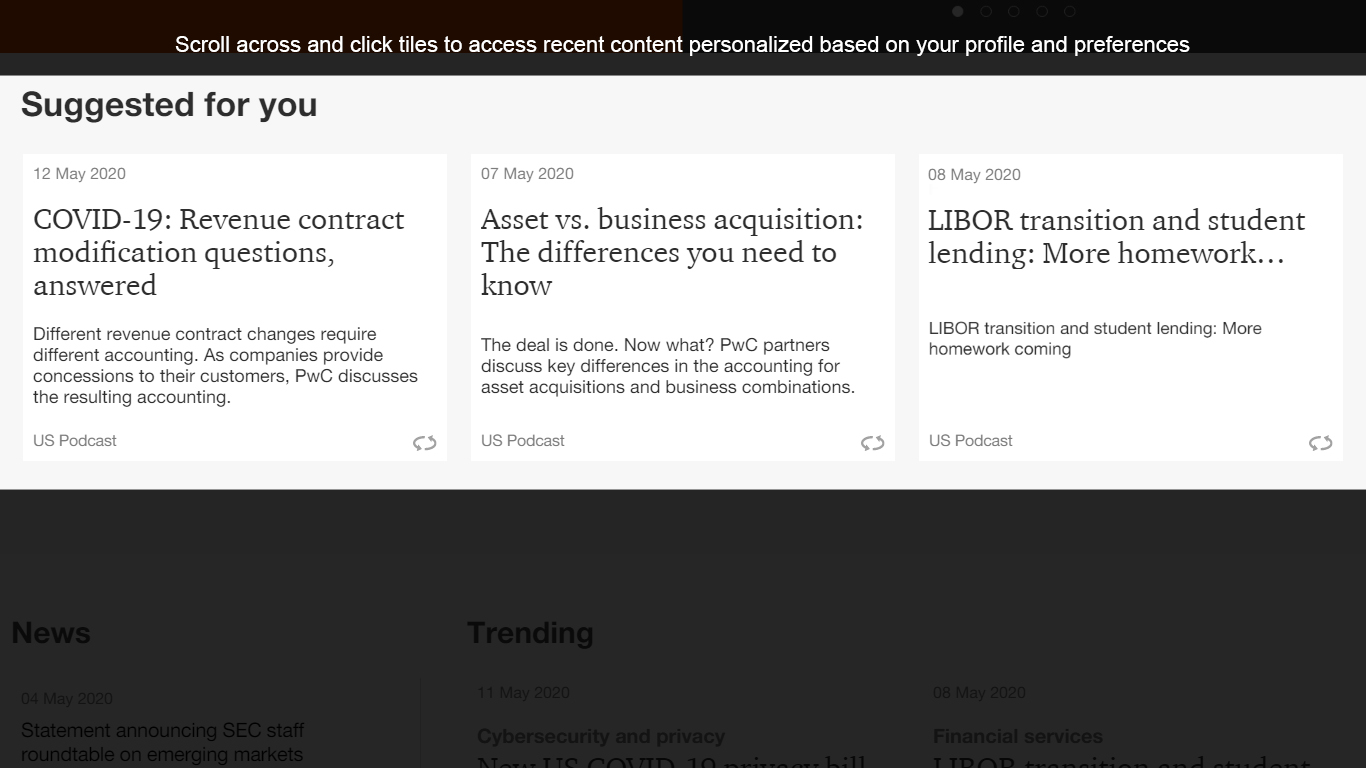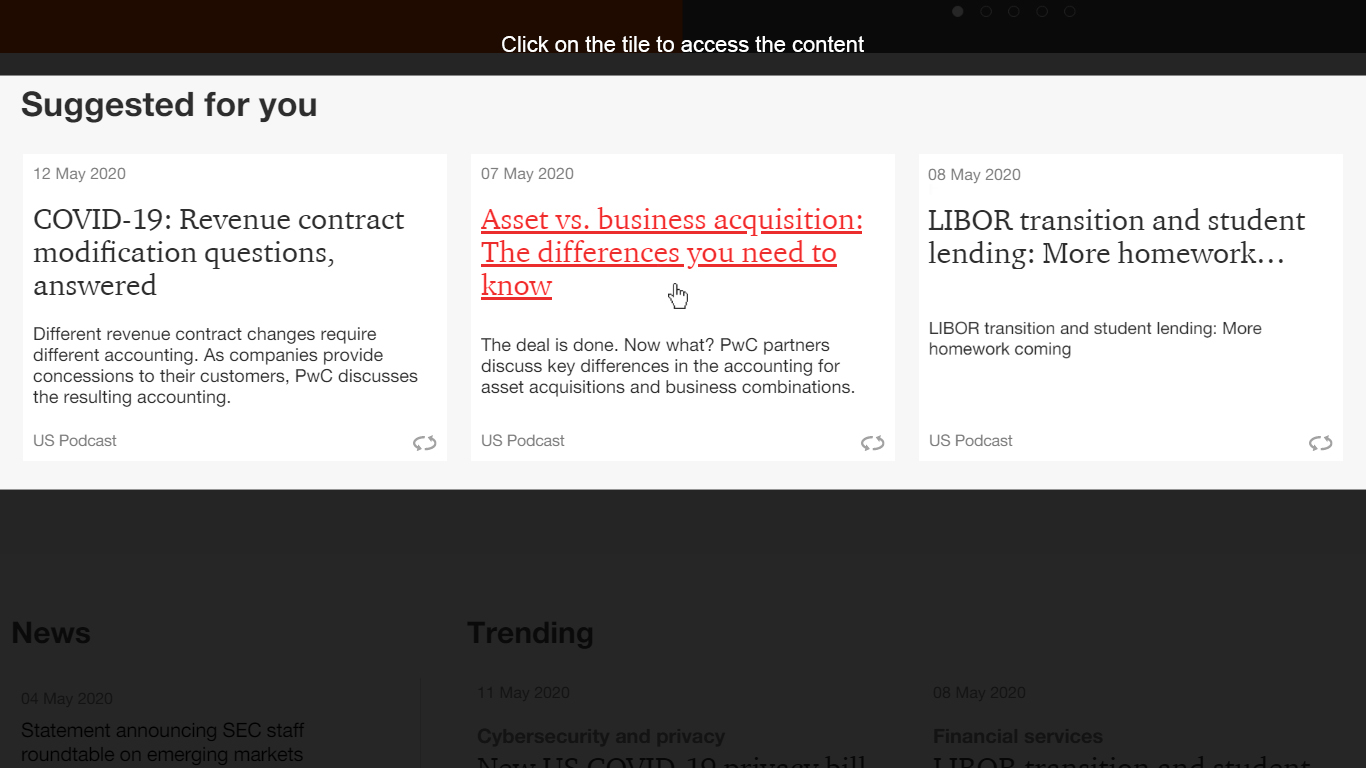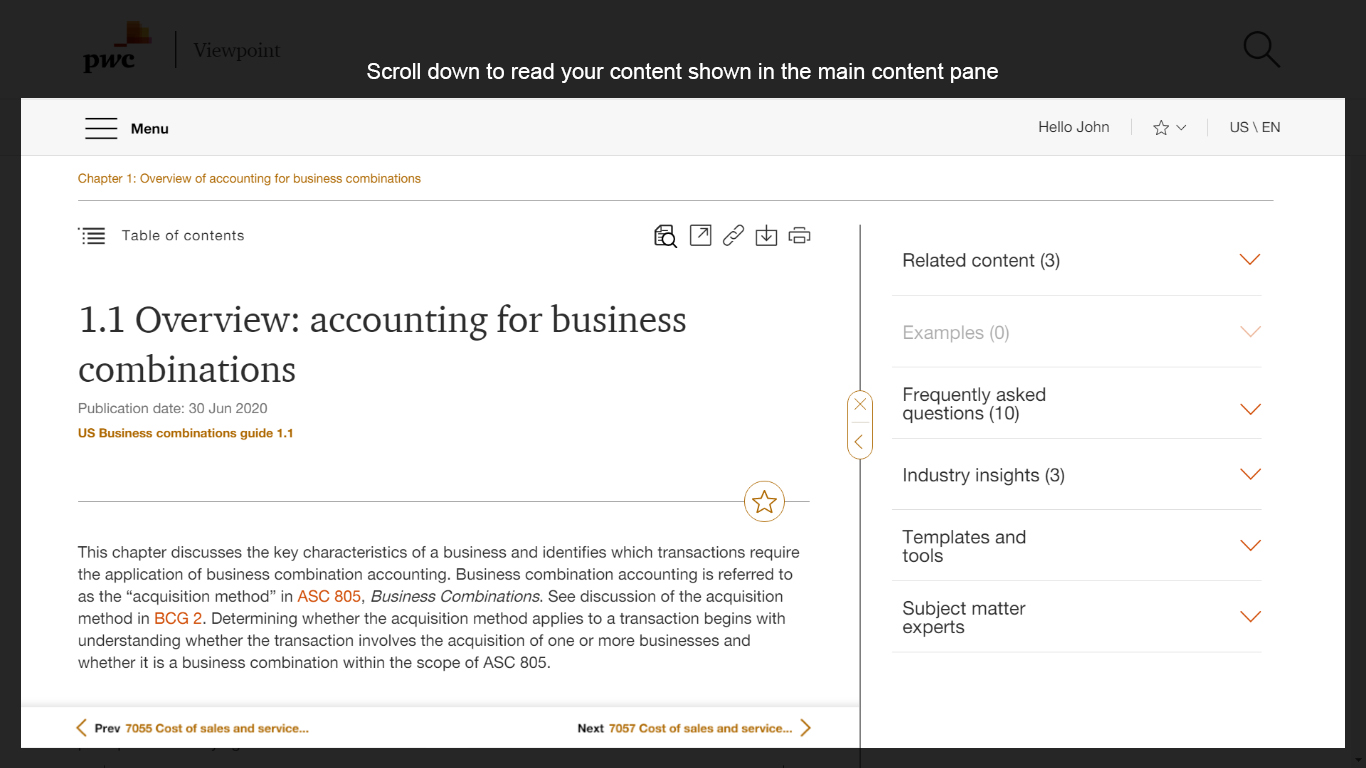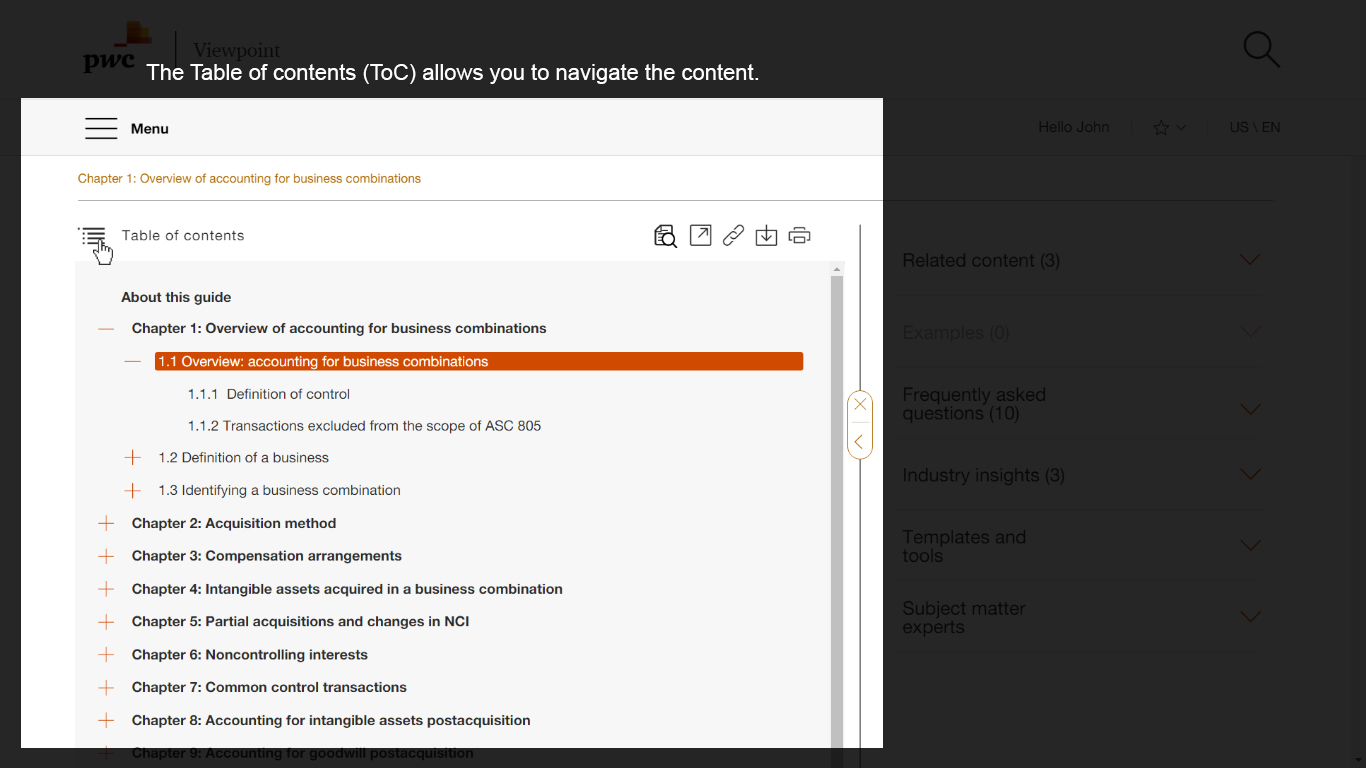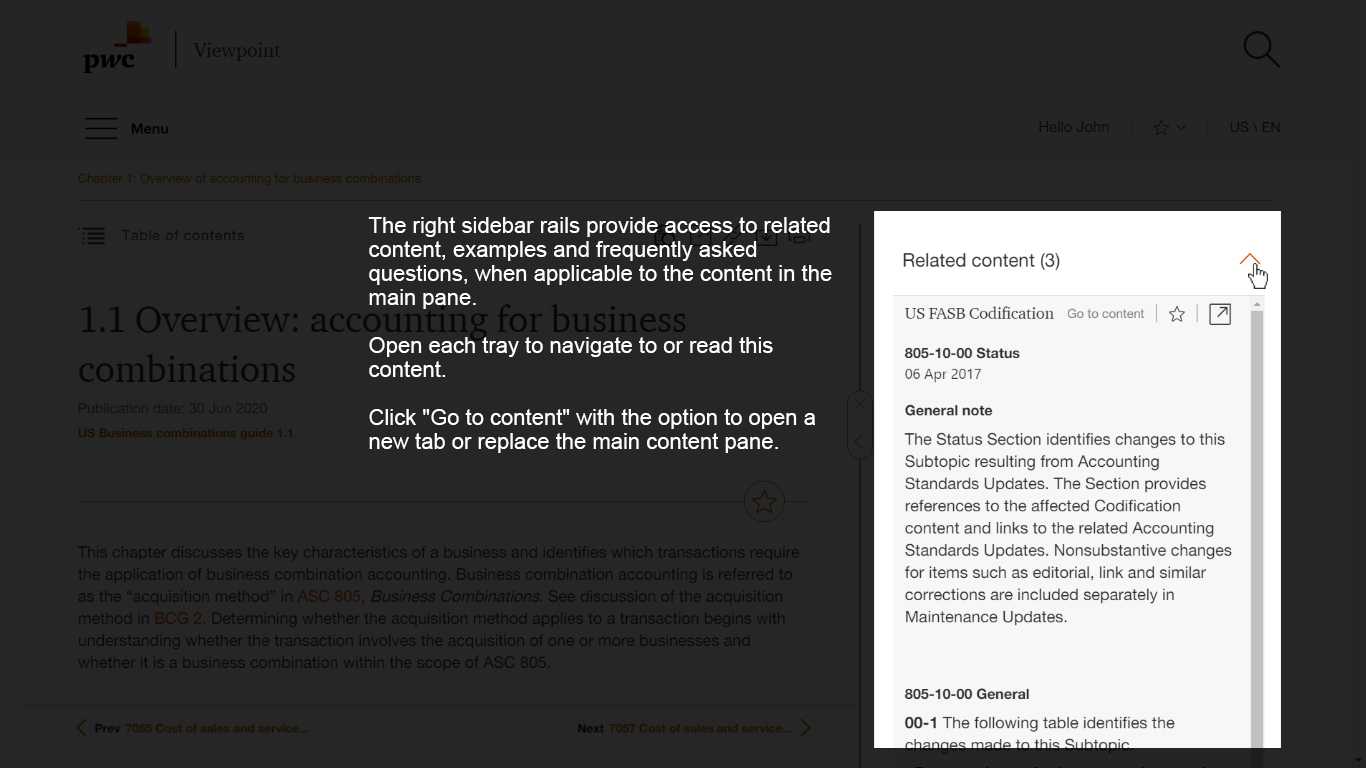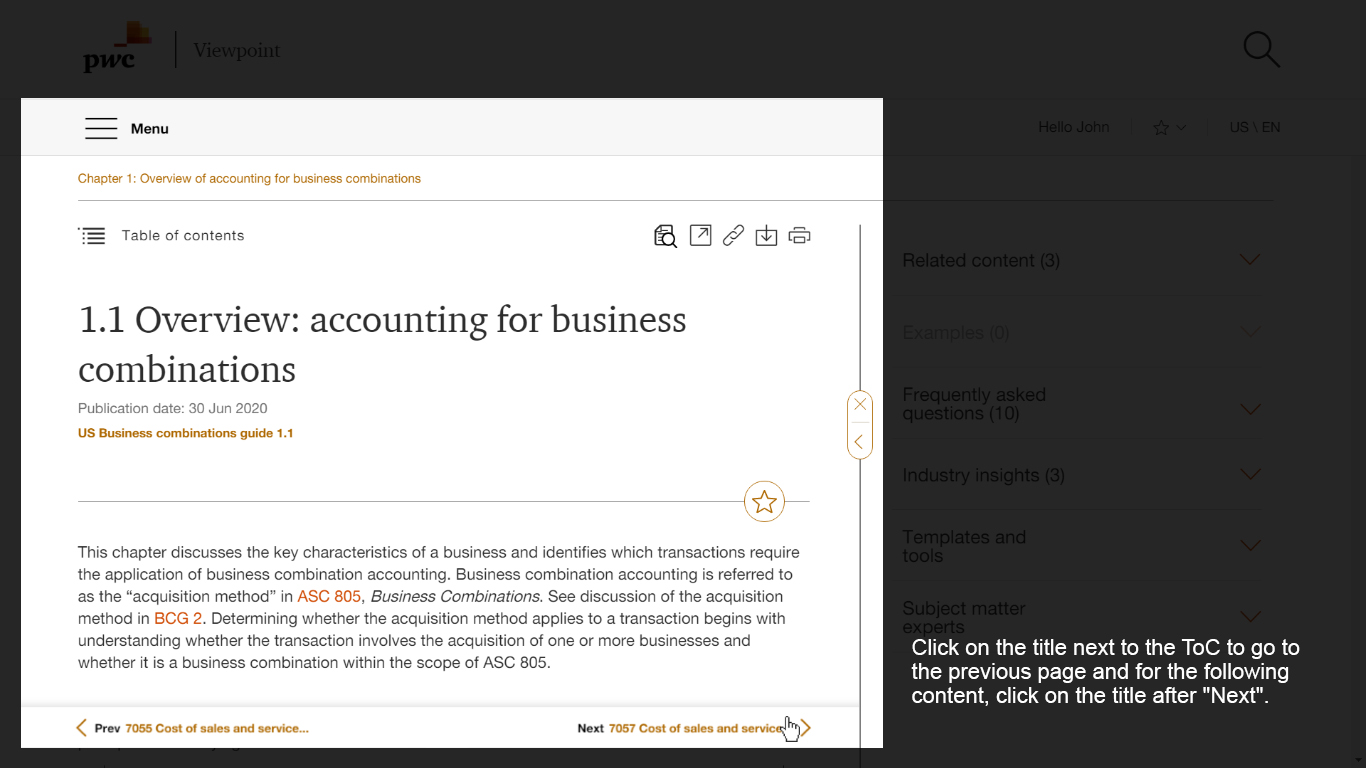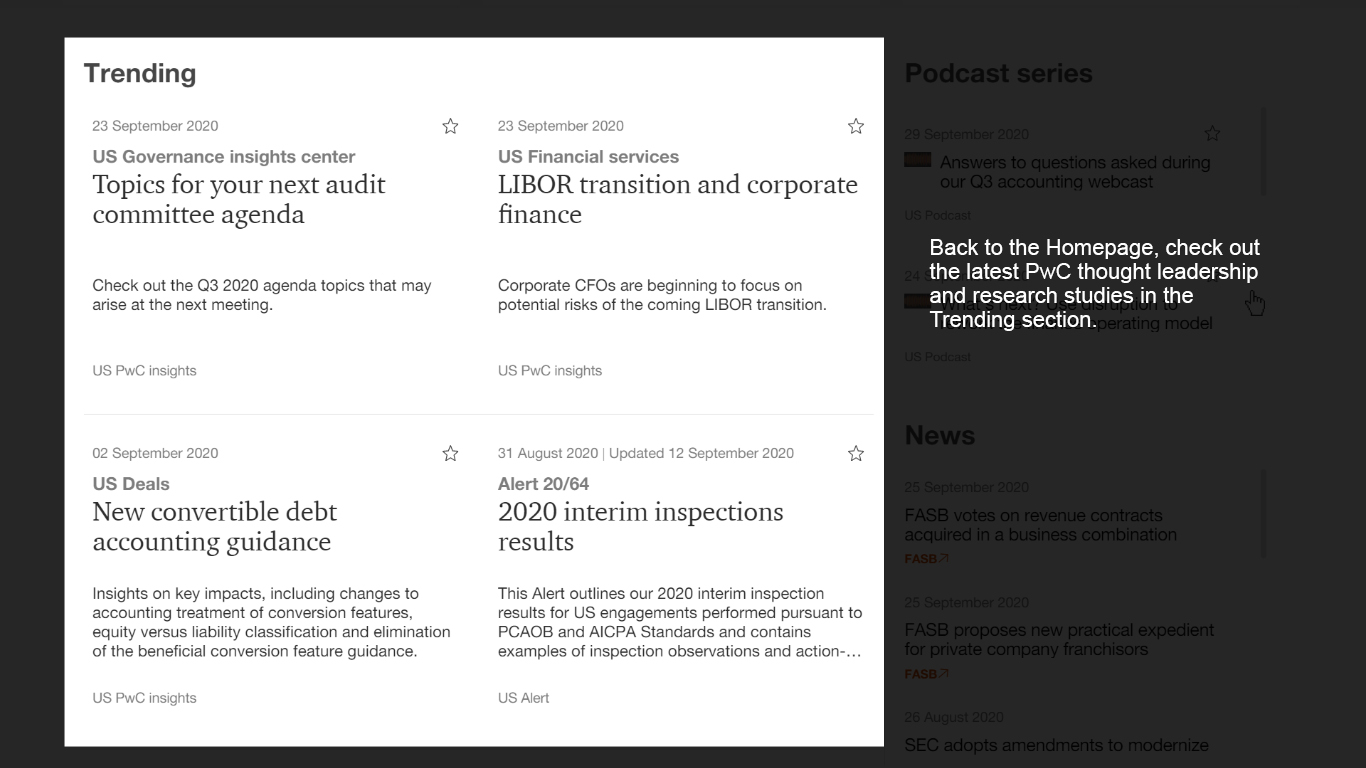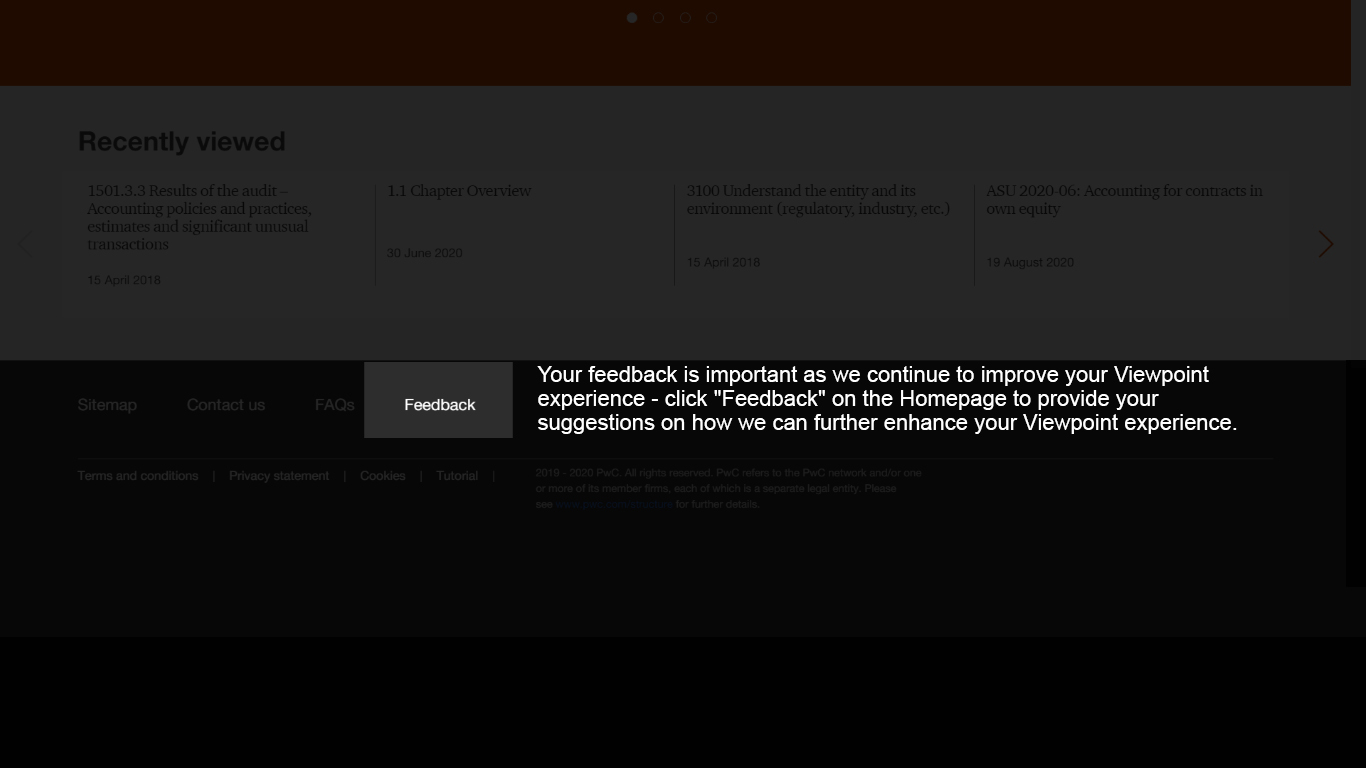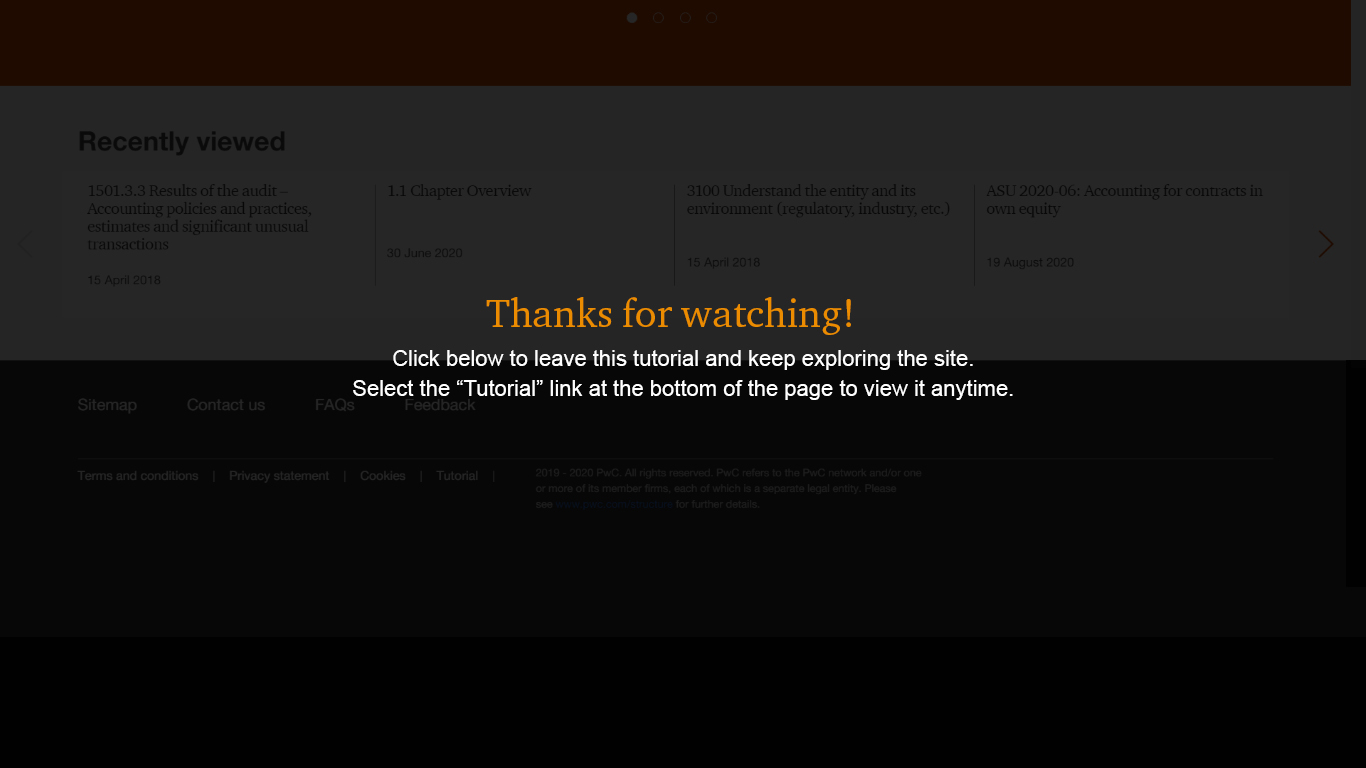このセクション内を検索
以下のセクションを選択して検索する用語を入力するか、または全体から検索する場合はこちらをクリック 日本基準トピックス
Favorited Content
取得時 |
|
移転時または払戻時 |
|
期末時* | 特定の電子決済手段の券面額に基づく価格をもって貸借対照表価額とする。 |
発行時 |
|
払戻時 | 特定の電子決済手段の受渡日に払戻しに対応する債務額を取り崩す。 |
期末時 | 特定の電子決済手段に係る払戻義務は、債務額をもって貸借対照表価額とする。 |
外貨建電子決済手段(資産) | 期末において、本実務対応報告の対象となる外貨建電子決済手段(以下、「対象外貨建電子決済手段」とする)の円換算は、外貨建取引等会計処理基準 一 2 (1) ①の定めに準じ、決算時の為替相場による円換算額を付する |
払戻義務(負債) | 期末において、対象外貨建電子決済手段に係る払戻義務の円換算は、外貨建取引等会計処理基準 一 2 (1) ②の定めに従って、決算時の為替相場による円換算額を付する。 |
|
_______________________________________________________________ |
PricewaterhouseCoopers LLP

以下のセクションを選択して検索する用語を入力するか、または全体から検索する場合はこちらをクリック 日本基準トピックス