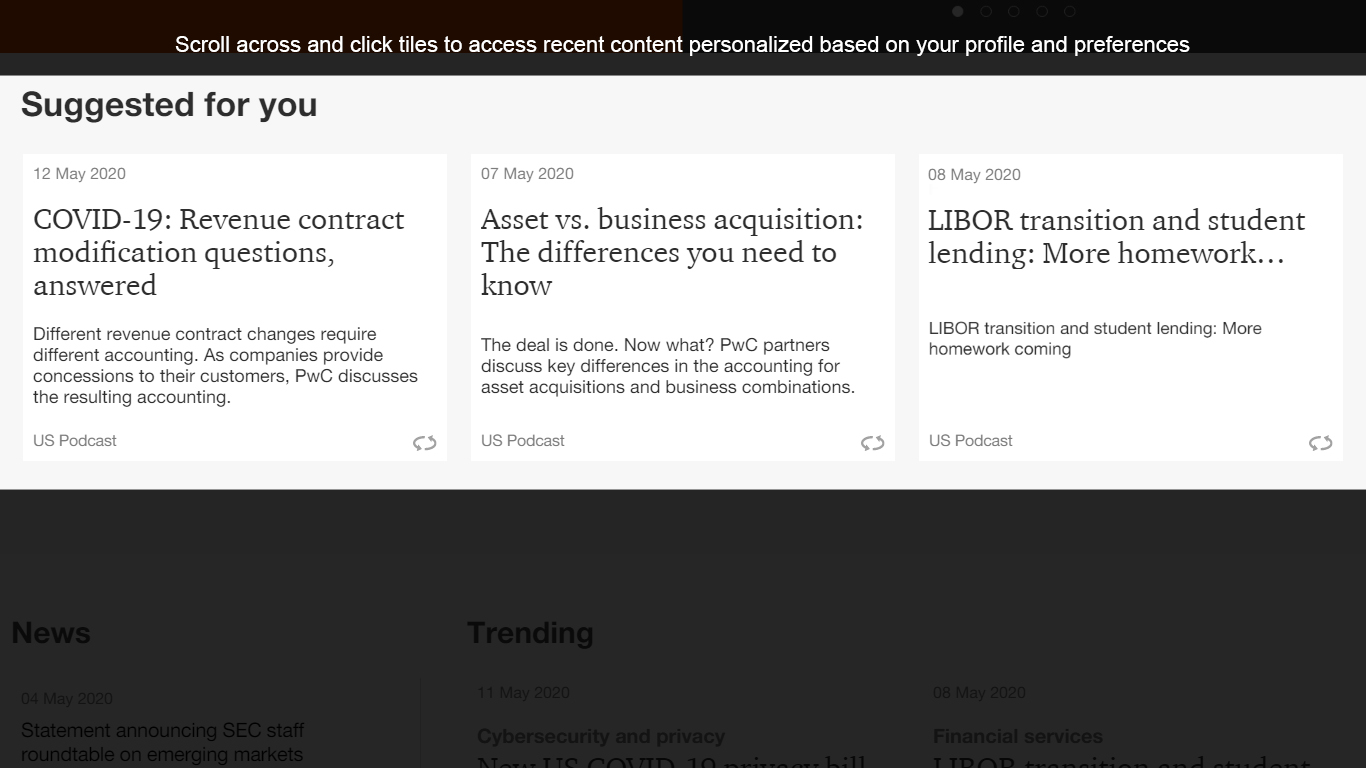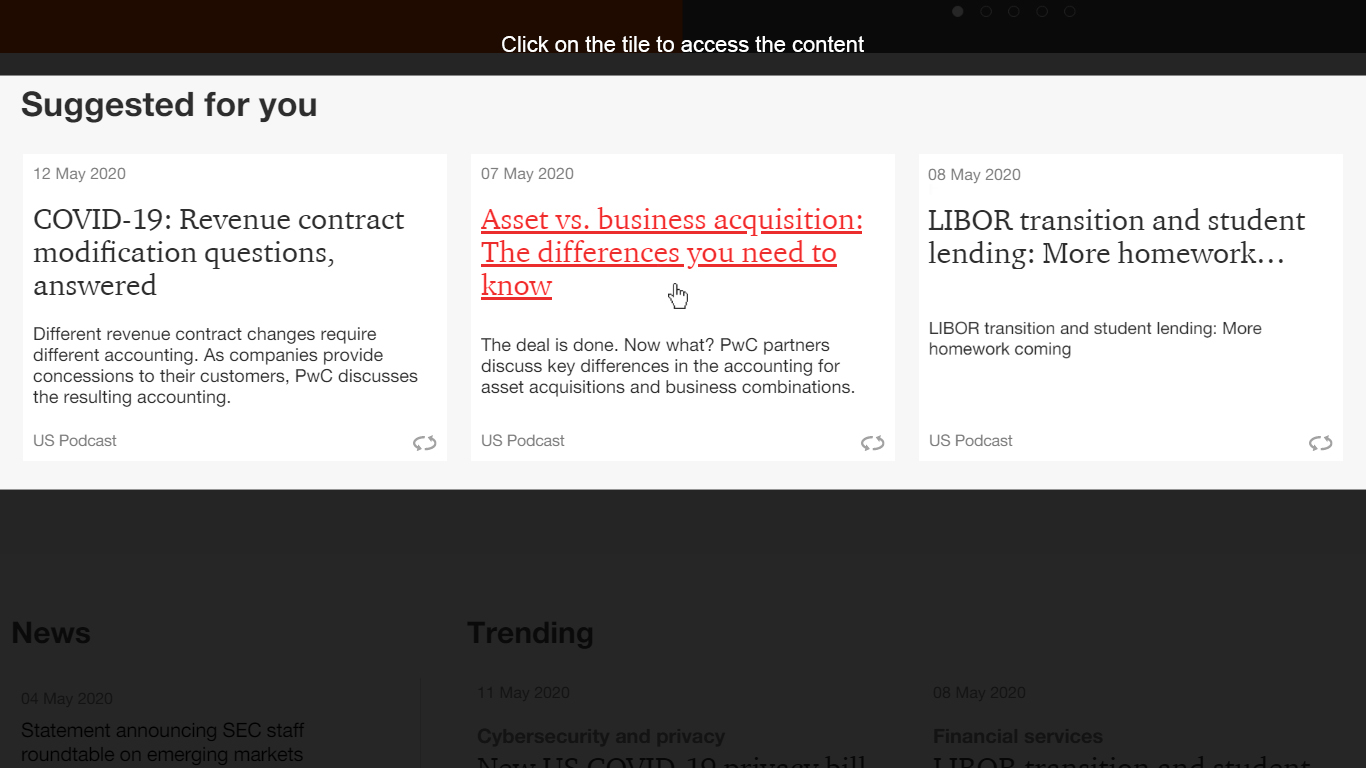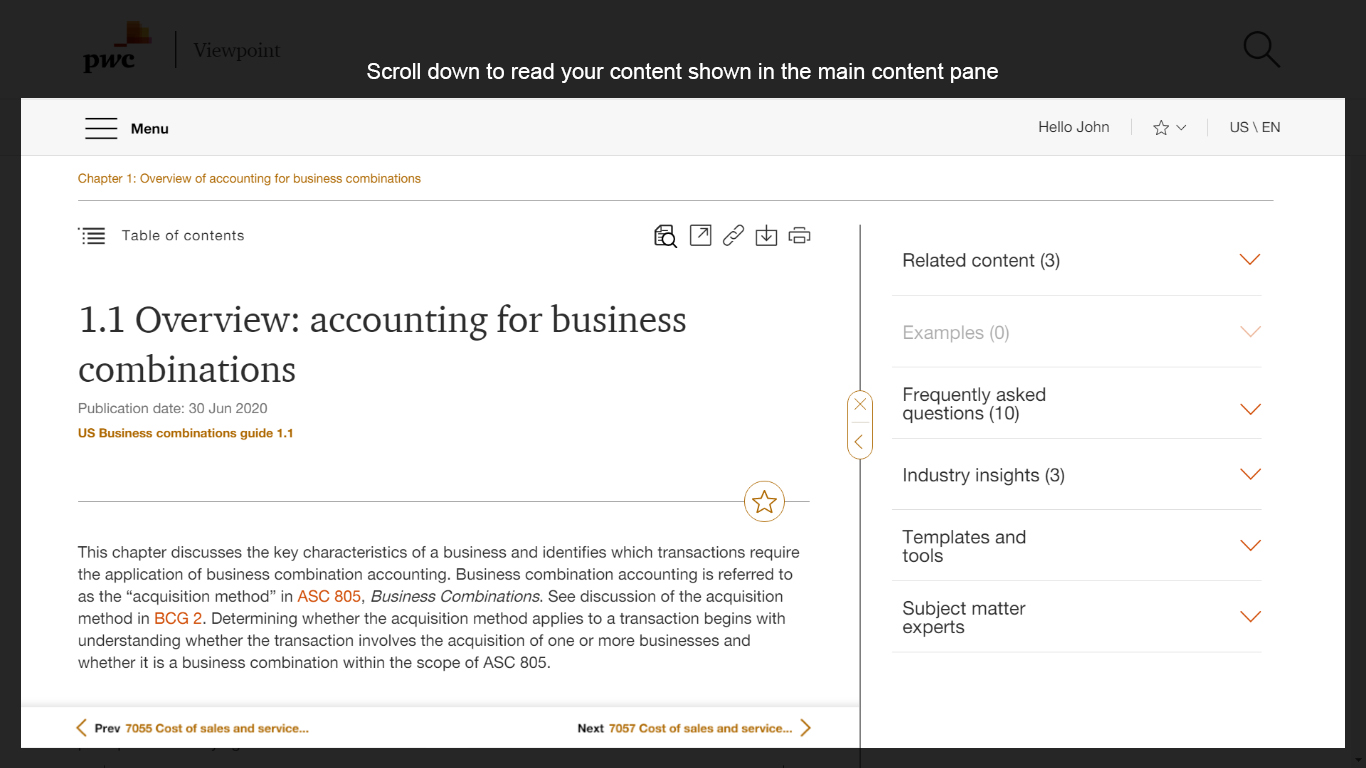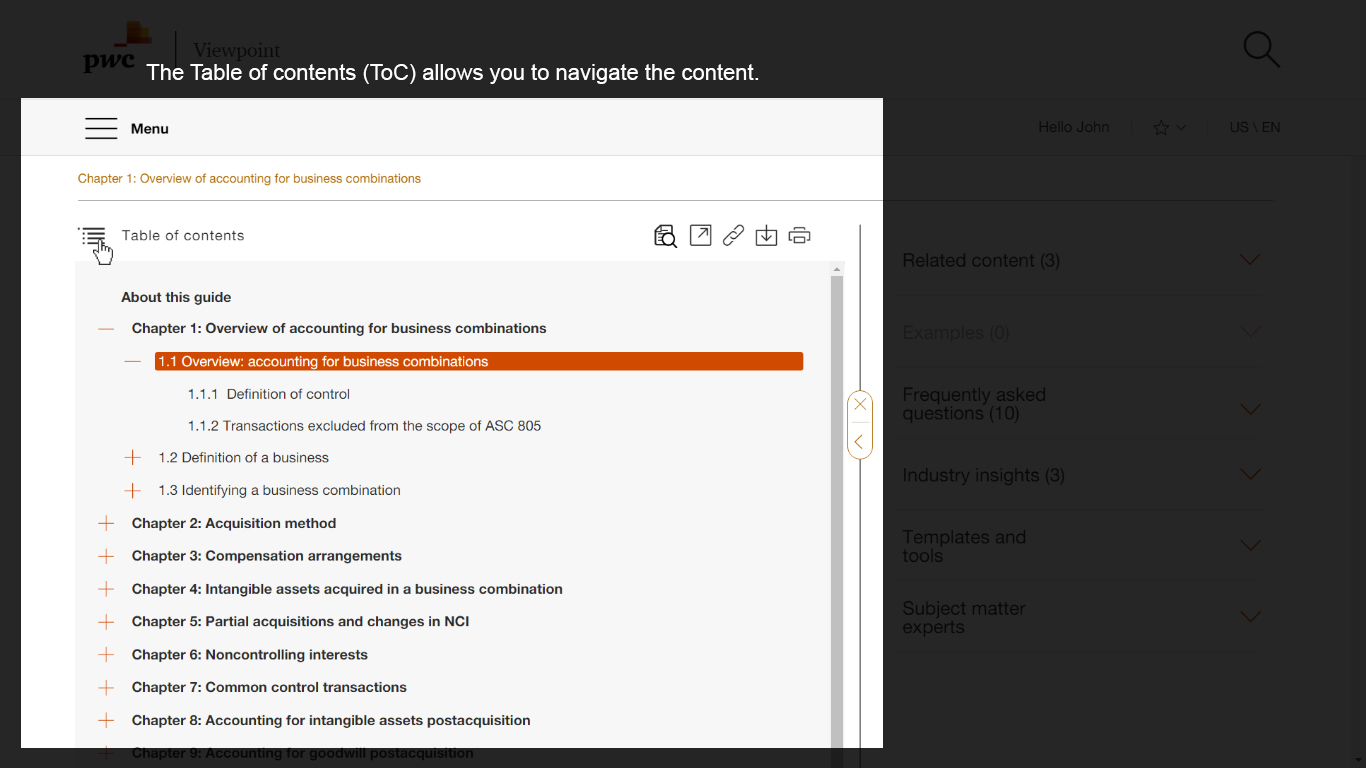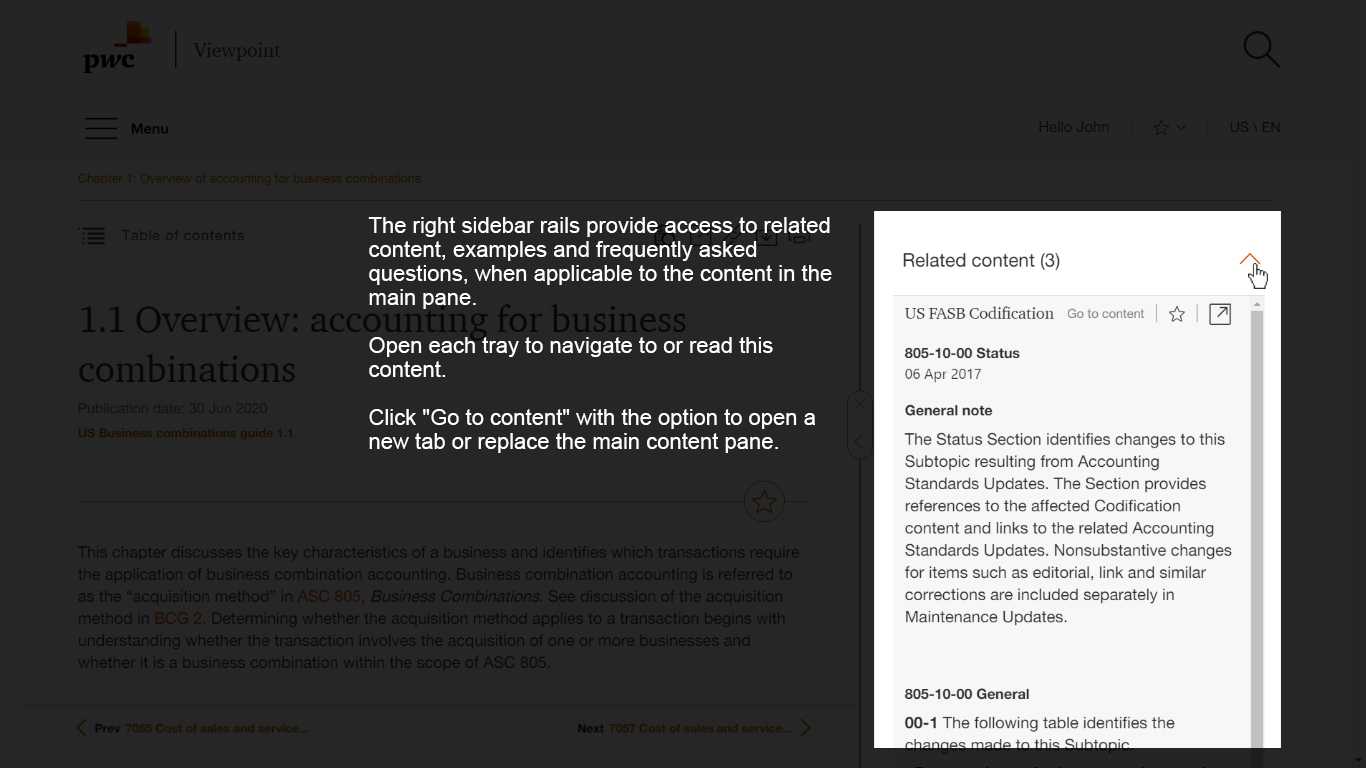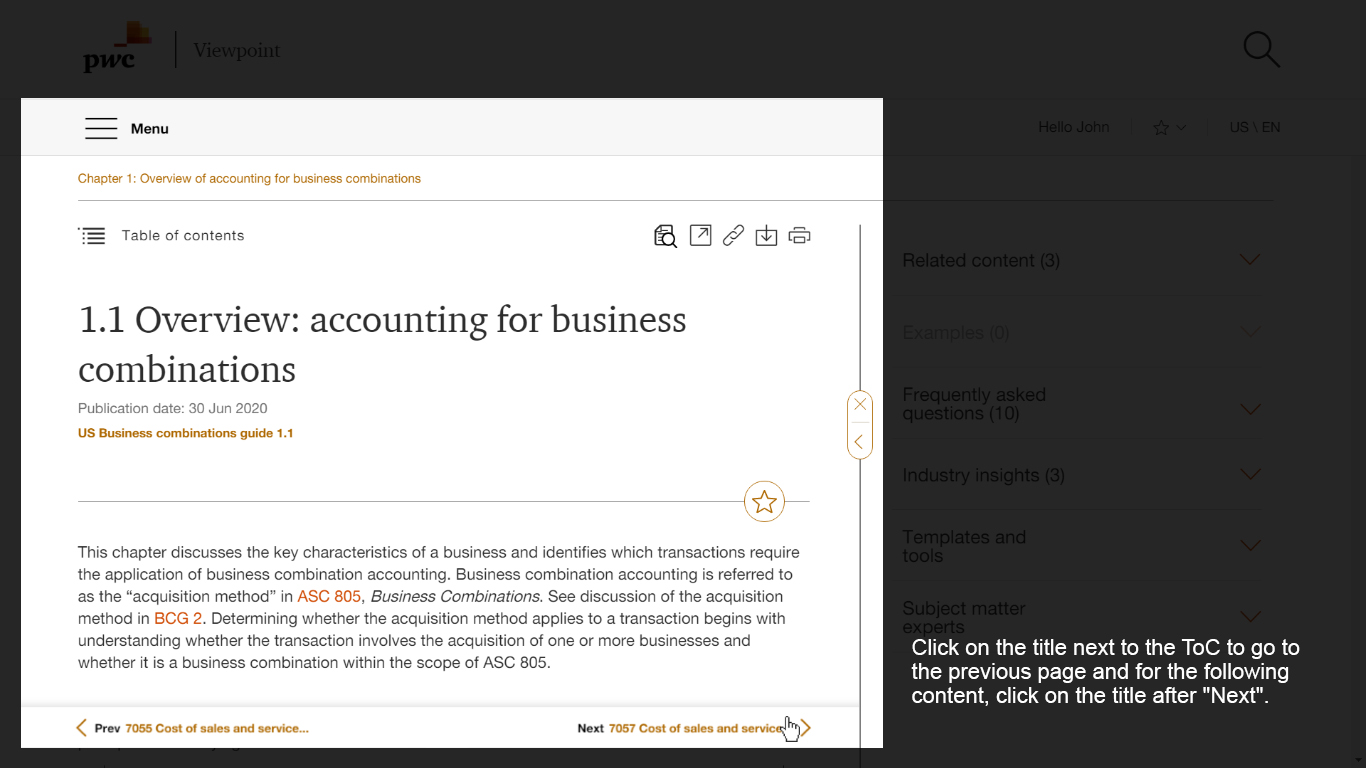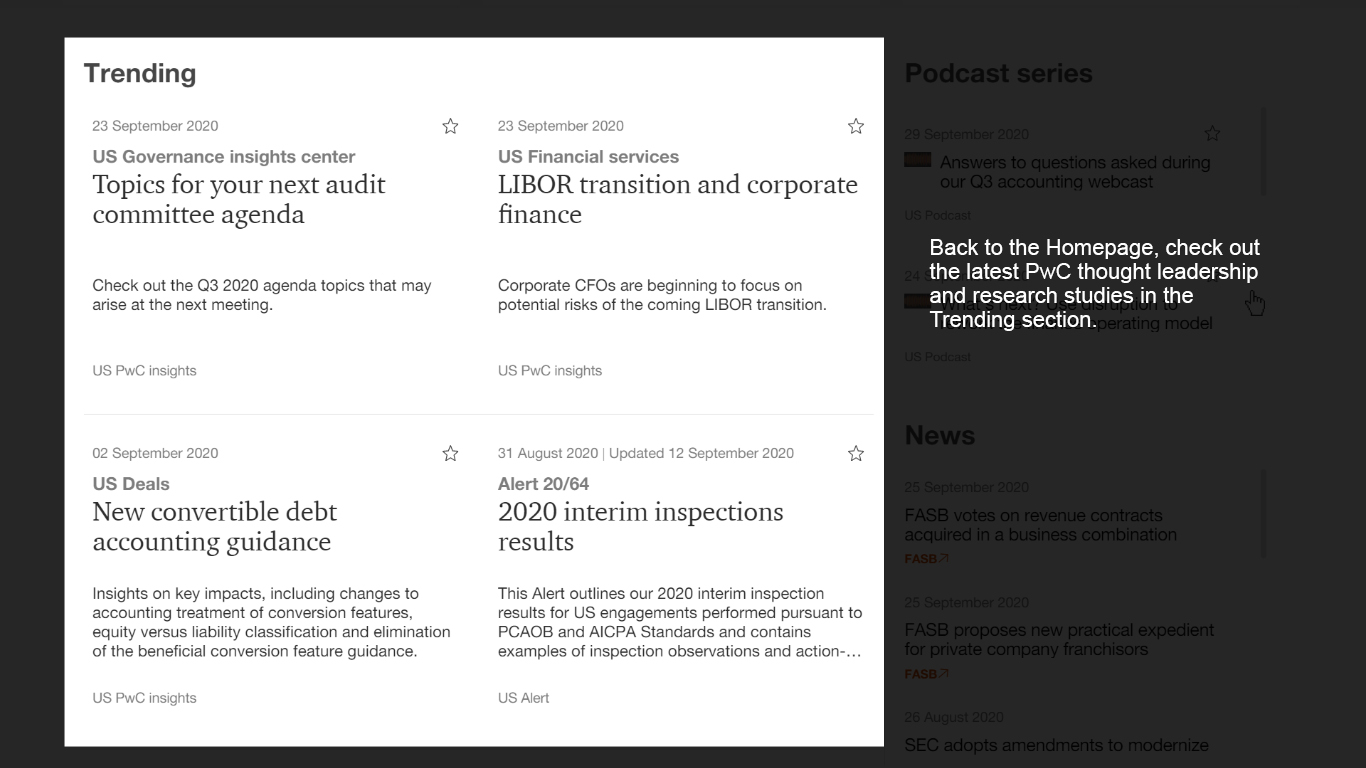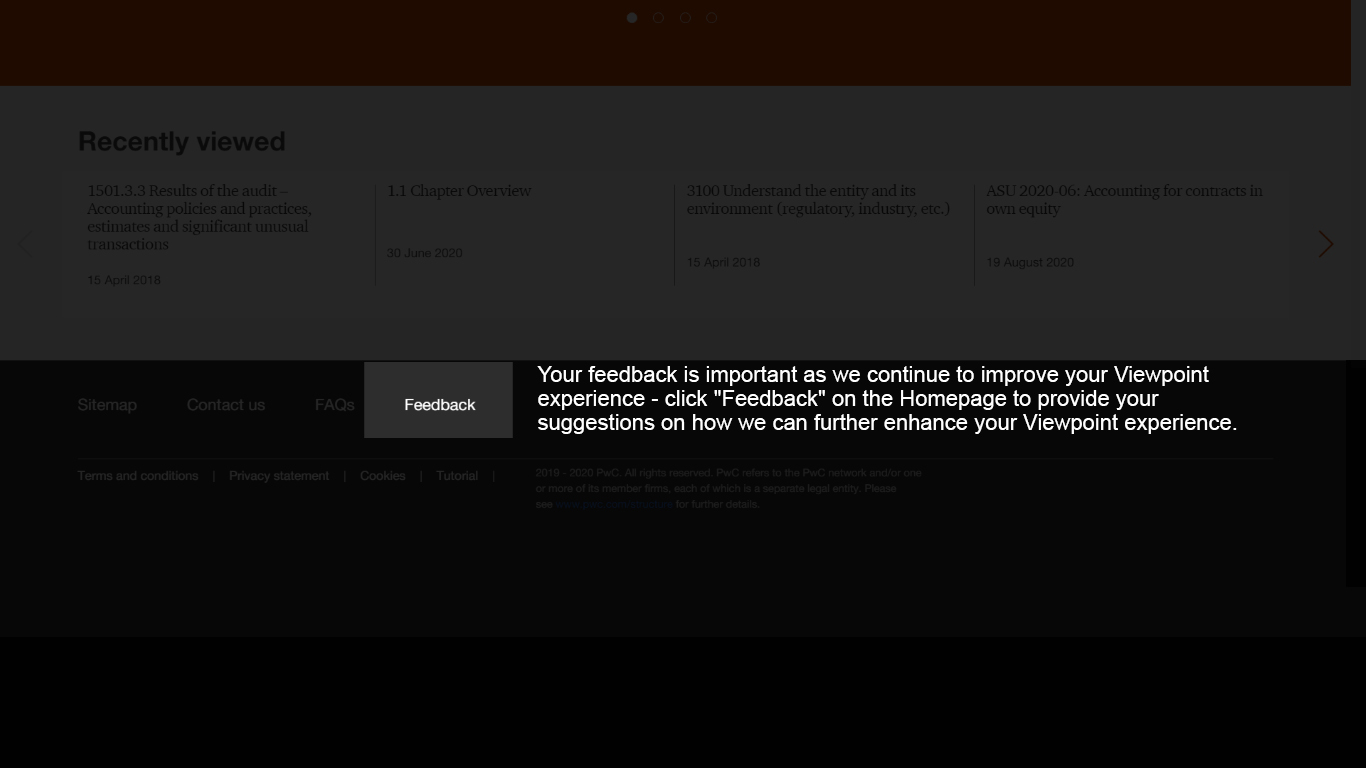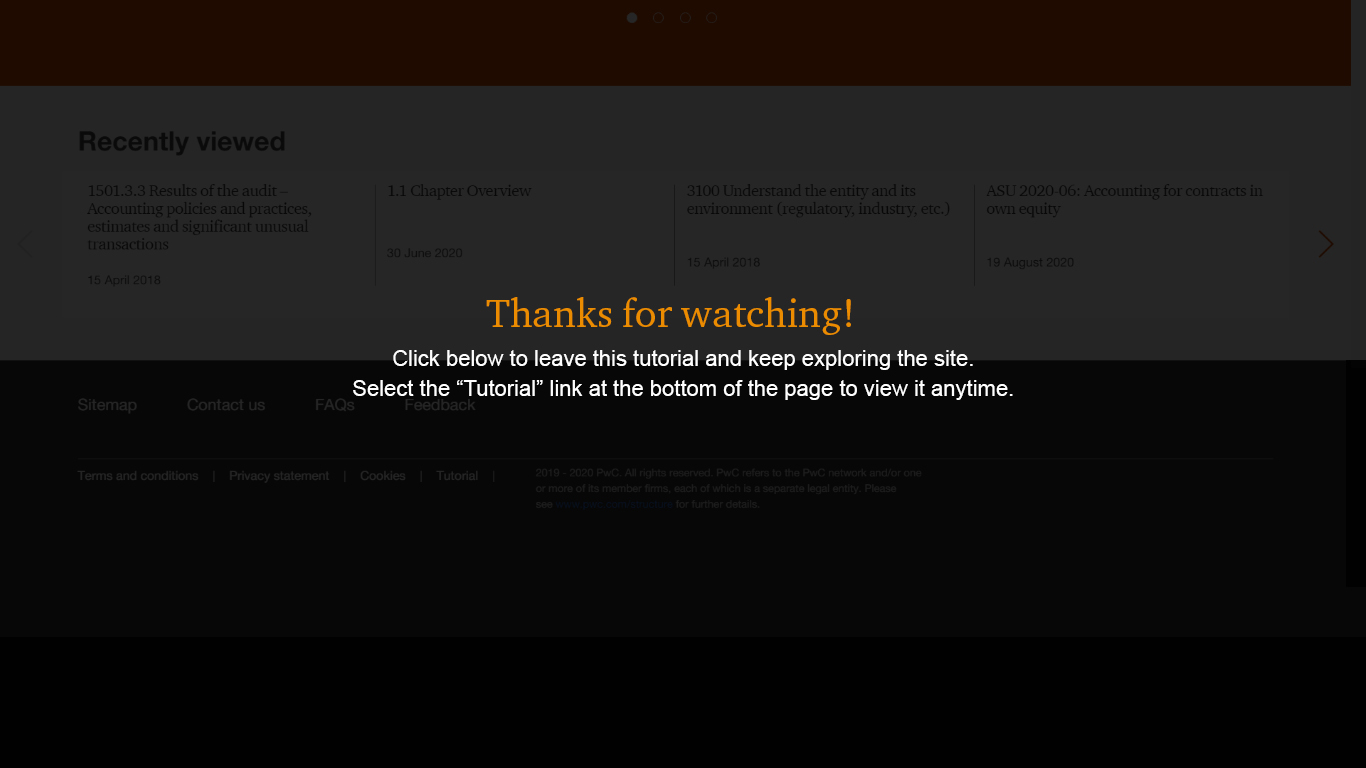⇒原文(英語)はこちらへ
要点
利害関係者は特にパリ協定準拠の仮定(Paris Aligned Assumptions)に注目しています。本資料は、IFRSに基づき財務報告を行う企業が検討するさまざまな事項を要約したものです。
論点
パリ協定とは何か
2020年以降の新たな国際的枠組みであるパリ協定には、190か国と欧州連合(EU)が署名し、温室効果ガス(GHG)排出量および気候変動の影響の大幅削減という目標が掲げられています。
多くの国がパリ協定を採択し、国が決定する貢献(Nationally Determined Contribution: NDC)の一部として、2020年までに国連に対しGHG排出量削減計画を提出しています。NDCには、通常、2025年と2030年の中期目標、および遅くとも2050年までのGHG排出量ネットゼロ目標が含まれています。
各国は、それがNDCを達成するうえで十分かどうかはわからないものの、GHG削減に関連する詳細な法規則を導入している可能性があります。したがって、企業は、要求事項に対処するため、その要求事項や予想される影響に応じて、さまざまレベルで詳細な計画を設定することになります。
「パリ協定準拠の仮定(Paris Aligned Assumptions)」という用語は、企業がパリ協定の目標を考慮して見積りを行う際に用いられるインプットをいいます。
財務諸表利用者は何を期待しているか
財務諸表利用者は、気候変動が財務諸表に織り込まれているかどうか、またどのように織り込まれているのかについて、企業、経営者、取締役、および監査人に対し、ますます厳しい目を向けています。パリ協定が財務諸表に重要性のある影響を及ぼす場合がありますが、「この財務諸表はパリ協定に準拠しているのか」という問いに対する答えは、問いの見た目よりも複雑である場合が多く、また、基本的にIFRSにおけるさまざまな会計基準のテクニカルな要求事項により導き出されます。
IFRSに基づき検討すべきガイダンスは何か
国際会計基準審議会(IASB)は、教育文書を作成し公表しています。この教育文書には、さまざまな基準書における測定および開示に関する要求事項に対して気候関連リスクがどのような影響を及ぼす可能性があるのか、および気候関連リスクをどのように織り込むべきかを判断する際に参照される各基準書のさまざまな項番号について、リスト(網羅的なものではない)が記載されています。PwCでは、In brief INT2020-14「
IASBの教育文書:気候関連問題がIFRSを適用して作成された財務諸表に与える影響」(和訳は
こちら)において、これらの要求事項をまとめています。
IASBはまた、アジェンダに気候関連リスクに関するプロジェクトを追加するかどうかを検討しています。IASBは、第3次アジェンダ協議において、アジェンダ協議の情報要請に関するアウトリーチの際に、特定の投資者から次のような意見があったと述べました。
(a)財務諸表に計上される資産・負債の帳簿価額に対する気候関連リスクの影響について、定性的・定量的情報の改善が必要である。当該事項に関する開示や情報は、比較可能で首尾一貫していなければならない。
(b)気候関連リスクは、発生可能性がほとんどない長期的なリスクとして認識される場合が多く、将来の見積りを要求する財務諸表の領域(例えば、資産の減損テスト)において十分に検討されない可能性がある。
アジェンダ協議では改善の余地のあるさまざまな領域が提起されており、IAS第1号「財務諸表の表示」で要求されている不確実性に関する情報を開示するための閾値の検討、資産の減損テストにおける使用価値に関する要求事項の拡大、汚染物質の価格決定メカニズムの会計処理に関する追加のガイダンスの開発などが含まれます。IFRSを改善するにあたり、IASBは、アジェンダにプロジェクトを追加し、IFRSの修正のためのデュー・プロセスを経る必要があります。
しかし、その一方で、パリ協定によるさまざまな影響のうち、既存の基準書に基づき検討する必要のあるものも依然としてあります。
どのような影響が予想されるか
パリ協定は企業によって異なる影響がありますが、気候関連リスクの高い業種に属する企業は他の業種に属する企業よりも影響を受ける可能性が高いといえます。また、会計および開示への影響は、個々の事実および状況(例えば、企業の計画や関連する国の規制)によって、または、場合によっては、市場参加者がパリ協定による企業への影響をどのように見るのかによっても異なるといえます。したがって、企業が「パリ協定準拠の仮定」を会計記録に反映させているかどうかが問われる可能性があったとして、その問いが示すほど、その答えは概して単純ではありません。
一般的に、パリ協定が企業に及ぼす影響として、資産および負債の認識または認識の中止、当該資産および負債の測定、ならびに表示および開示への影響が考えられます。しかし、認識、認識の中止、測定方法ならびに開示要求は会計基準によって異なるため、その影響は資産または負債の性質によって異なるといえます。
どのような測定の検討事項があるか
事実および状況によって異なる測定の検討事項が適用される可能性があります。以下の例は、包括的なリストではなく、関連するIFRSを適用した場合に異なる影響が生じる可能性があることを示しています。
公正価値測定
IFRS第13号「公正価値測定」は、特定の資産に関する仮想的な売却取引に基づいています。簡単な例として、IFRS第9号「金融商品」に基づき純損益を通じて公正価値で測定するものとして会計処理されている、石油・ガスの公開企業の株式投資が挙げられます。このような投資の公正価値は、通常、活発な市場における相場価格を参照することにより決定され(すなわち、レベル1の公正価値測定)、したがって、気候関連リスクを含む異なるリスクに関する市場参加者の仮定を反映することになります。相場価格を使用しなければならず、これに気候関連リスクに関する市場参加者の仮定が反映されるべきであるため、それ以上の調整を行うことはできません。
活発な市場における相場価格が入手可能でない場合、公正価値モデル(レベル2またはレベル3)に、仮想的な出口取引において市場参加者が気候変動をどのように考慮するかの仮定を織り込む必要があります。つまり、企業は、市場参加者が考えるよりも保守的または楽観的な企業固有の仮定を用いるべきではありません。活発な市場で取引されていない項目の公正価値の決定には、明らかに重大な経営者の判断が必要となる可能性があり、インプットまたは仮定(気候を含む)に関する適切な開示を検討する必要があります。
IAS第36号-非金融資産の減損
IAS第36号「資産の減損」は、企業に対して、非金融資産に減損の兆候があるか評価することを要求しています。このような兆候の評価においては、パリ協定が資産または資金生成単位の回収可能性に及ぼす可能性のある負の影響に関する見積りを考慮する可能性があります。したがって、パリ協定は、IAS第36号の範囲に含まれる資産の減損に係る評価が行われるかどうか、またどの程度の頻度で行われるかに影響を与える可能性があります(PwC IFRSマニュアルEX 24.12.2参照)。
ただし、IAS第36号に基づく資産の回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか金額が高い方で決定され、その後、この金額の高い方が、資産または資金生成単位の帳簿価額と比較されます。上述のように、公正価値測定は市場に基づく測定であり、企業固有の測定ではありません。したがって、企業は、主要な市場における、または主要な市場が存在しない場合には最も有利な市場における、秩序ある取引において、どのような資産(または、資金生成単位)が売却され得るかを見積もることが必要といえます。公正価値測定では、それが市場参加者によって想定されるのであれば、資産の運用における将来の改良を考慮することができます(例えば、燃焼エンジン・プラントの電気自動車プラントへの再利用)。
使用価値には一定の制約があり、確約されるまでは改良による変更を考慮に入れることが認められません。しかし、使用価値には、気候変動に関するその他の見積り、およびそれらの見積りが資産または資金生成単位に関連する将来キャッシュ・フローにどのような影響を与えるかを考慮することになります。
最善の見積りを要求する基準書
いくつかのIFRS基準書では、測定に最善の見積りを織り込むことを要求しています。例えば、IAS第16号「有形固定資産」は、資産の耐用年数の最善の見積りを考慮することを要求しています。後述のように、最善の見積りが用いられている場合は、財務諸表に首尾一貫性が必要となります。耐用年数について複数の結果が生じる可能性がある場合、最も可能性の高い仮定を用いる可能性があります。または、確率加重平均が最善の見積りとなる可能性も考えられます。もし気候の影響が重大であればシナリオに織り込む必要がありますが、企業の最善の見積りを導き出すためにその影響を確率加重することがあります。
使用期間が物理的な耐用年数である40年となる可能性が75%で、パリ協定の結果生じる可能性のある将来の法規制の変更により使用期間が25年となる可能性が25%である資産を考えてみます。企業はその最善の見積りに基づき当該資産の耐用年数に40年を使用する可能性があります。その一方、企業が確率加重された結果を用いる場合は、見積耐用年数として約36年間を使用することになります。
最善の見積りと著しく異なる結果が生じる(たとえば、見積りに著しいばらつきがある)場合、企業は、耐用年数の見積りに確率加重アプローチを用いる方が適切かどうか、または最善の見積りアプローチを用いるのであれば見積りの変更のリスクに関する追加的な開示が必要かどうかを検討する必要があります。さらに、企業は、新たな情報が入手可能となった場合は可能性の再評価を必ず行うとともに、重大な不確実性が存在する場合には、より頻繁に、または、より詳細に再評価を行う必要があります。
どのような開示の検討事項があるか
企業は、財務諸表の作成基礎となる気候関連の仮定を投資家が理解できるような開示がIFRSに基づき要求されているかどうかを評価しなければなりません。
その起点は、特に資産または負債の測定に適用される基準書の開示要求であるべきです。さらに、重大な判断および見積りの開示に関するIAS第1号の全般的な要求事項は、実施された見積りの感応度の検討も含めて考慮される必要があります。企業は、「パリ協定準拠の仮定」および関連するNDCに関する開示の必要性を評価する場合、GHG排出量削減に対する当該仮定の適用について、以下を検討する必要があります。
- 企業の現行の計画を大幅に変更する必要があるか
- 適用に多大なコストと時間が必要となるか
- 不確実性が高まり、ある項目の測定を決定する際に適用されるシナリオの数が増えるか
- サプライヤーのコストや製品または業務に著しい影響を与えるか
主要な仮定ではIFRSに準拠するために財務報告と非財務報告との間の整合性は必要であり、企業はこの整合性を確保する必要があります。例えば、企業がサステナビリティ報告書においてパリ協定の影響に関する最善の見積りを公表している一方で、あるIFRS基準書が測定で最善の見積りを使用することを要求している場合には、企業は、財務報告で用いている見積りとサステナビリティ報告書で開示している見積りとの間の整合性を検討する必要があるといえます。
(例えば、企業が市場参加者による別の仮定に依拠しているため)サステナビリティ報告書において財務報告で反映されていない記載がある場合、企業は、その項目が財務報告で異なる基礎に基づき反映された理由について、追加の記載が必要かどうかを検討しなければなりません。
誰がどのような影響を受けるか
要するに、企業は利害関係者の期待を理解し、IFRSにおける測定および開示の要求事項を注意深く検討することが重要です。
IFRSに基づき作成される財務諸表に「パリ協定準拠の仮定」を反映させるための単一のアプローチは存在しません。しかし、これは、「パリ協定準拠の仮定」を無視すべきであるという意味ではなく、反対に、それらの仮定の使用は、関連するIFRSの遵守を注意深く検討し評価する必要があることを端的に意味しています。
企業は、これらの財務報告上の検討事項、ならびに非財務報告上の検討事項との整合性について、利害関係者、基準設定主体および規制当局と開かれた対話を継続するべきです。